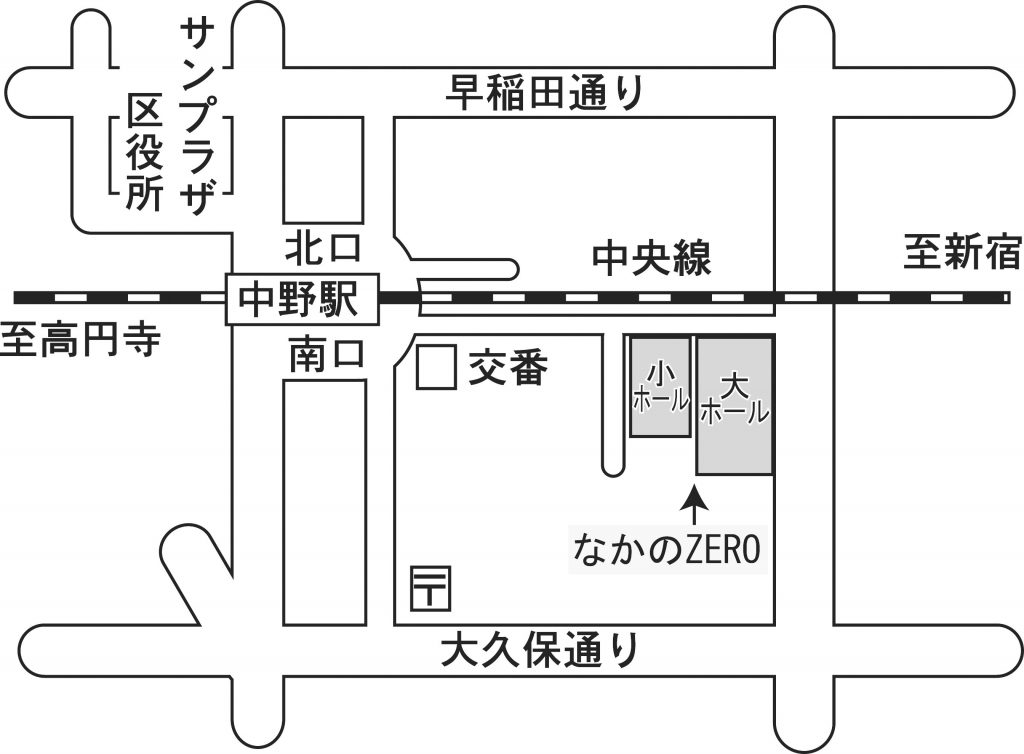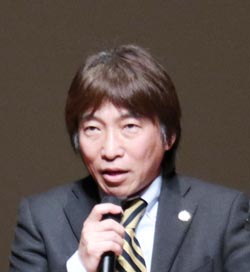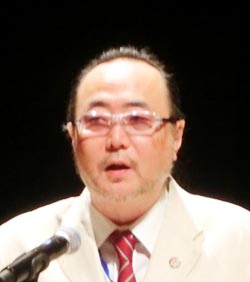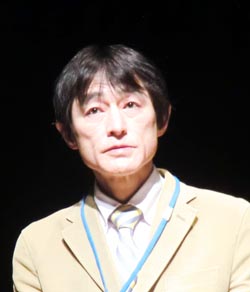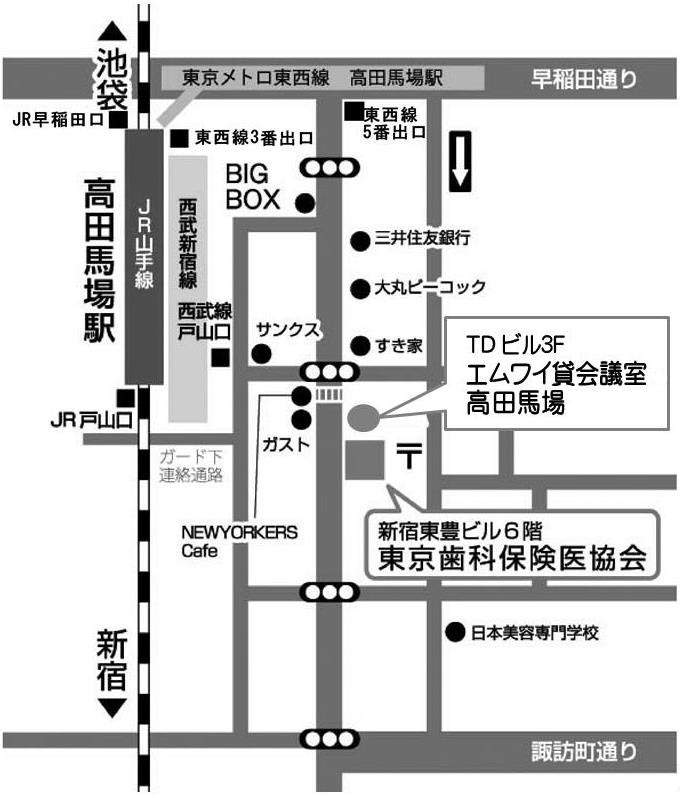10月8、9日、ウインクあいち(名古屋)において、第32回保団連医療研究フォーラムが開催され、全国から医師・歯科医師・スタッフ・一般市民など併せて826名が参加し、当協会からは11名が参加した。
8日は、保団連の住江憲勇会長と第32回保団連医療研究フォーラム実行委員長の荻野高敏愛知県保険医協会理事長、次回主務地を代表して沖縄県保険医協会の仲里尚実会長より挨拶が行われた。
その後、「今をどう生きる 子や孫が安心して暮らせる社会をどう残すか」をテーマとした記念対談が開催された。記念対談では、ノーベル物理学賞受賞の益川敏英氏と医師で作家の鎌田寛氏が登壇し、①子どもたちの未来を育てる、②科学との向き合い方、③平和への想いの3つの視点を中心に、ご自身の生い立ちや幼少期の様子から、平和への考え、日ごろの心に刻んでいることなどを語られた。その中で益川氏からは「子どもは育てるのではなく、自分で育っていくもの。子どもが飛びつくような種まきは必要だが、自立しはじめたら見守ることが重要である。私の場合はそれが本だった。本の向こう側には、無限の世界が広がっていると感じ、読書に夢中になった」と語られた。鎌田氏からは「権力に支配されていないか、時代の空気に支配されていないか、思い込みや偏見に支配されていないかということを常に心に刻んでいる。また、全員が誰かのためにと1%ずつ思えば、世界はずっと良くなる。社会の目にがんじがらめになってはいけない。」と語られた。
対談の最後には、若い医師に向けて、鎌田氏から「優れた技術を身に着けるとともに、心を診る職業であるので、心を失わずにいてほしい。常に自分以外の視点で物事を考えられる力が必要。自由な人間でいないと患者の自由が認められない。」と呼びかけた。
次いで、2017年4月~5月に全国の会員から30%無作為抽出し、ご協力いただいた「骨粗鬆症治療薬と顎骨壊死2017 実態・意識調査」の結果報告がされた。医科・歯科とも顎骨壊死の経験がある方の方が、ポジションペーパー2016の見解の変更について知っているという回答が高くなっており、関心が高くなることが示された。また、変更の賛同については、医科が54.6%、歯科が40.8%と医科の方が高かった。顎骨壊死を知った経緯について、医科では患者から聞いたが57.9%、歯科医師からの情報提供が42.1%という結果だった。一方、歯科からの顎骨壊死発症に関する処方医への情報提供は、56%は行われていたが、情報提供していないという回答が38.3%にも上った。
調査のまとめとして、「現在の骨粗鬆症薬は、注射や点滴での投与が増えており、お薬手帳では確認がしきれない。今回の調査でも、緊密な連携をとっているとは言い難い状況であり、保団連として、連携パスのようなものを作成してはどうか。」との提案がされ終了した。
9日の午前は分科会が開催され、東京歯科保険医協会からは5名5演題の発表があった。
第1分科会多職種連携では、高山史年理事が「経口維持加算における多職種会議等におけるシステム化の試み」の題で、ミールラウンドや多職種会議など一連の業務の効率化を図るべく行ったシステム開発について報告し、食支援の分野は歯科業界での中でも未開拓な部分であるが、将来的に最も必要とされる分野であり、積極的に参画してほしいと呼びかけた。
第2分科会高齢者医療・介護では、小林顕氏が「オーラルフレイルの主観的判断について」の題で、実症例を紹介しながら、口腔機能の低下が疑われる場合の精査の適応の可能性や、高齢者の多数歯欠如と口腔機能の低下の関連などについて考察を述べた。
第5、第6分科会歯科診療の研究と工夫では今西祐介氏が「それでも抜かないわけがある2017」の題で定期予防、歯牙再建、コンフォートブリッジ等を用いて抜歯をしない方法を紹介。歯根膜の保存はその後の人生において重要であり、保存か抜歯かの選択を任される歯科医師の責任は非常に重いと訴えかけた。また、横山康弘理事が「超高齢者の咬合採得の一例」の題で、実際の症例を紹介しながら、義歯作成における咬合採得の方法を述べた。自身が用いている用具などについても併せて紹介した。また、加藤開理事が「歯科用金属アレルギー患者に対する、医科歯科連携の実際」の題で、実際の症例を示しながら、金属アレルギー検査の依頼と問題点などを述べ、併せてメタルフリーにした症例を紹介した。





左から、高山先生、小林先生、今西先生、横山先生、加藤先生
午後は、「医療従事者の働き方はこれで良いのか?~良質なキュアとケアは、良質な労働環境でこそ~」 「地域包括ケアの現状と課題~3つの地域からの提言~」「子どもの貧困と健康~医療者としてどう支援できるのか~」の3つのシンポジウムが開催され、2日間にわたる医療研は終了した。
「地域包括ケアの現状と課題~3つの地域からの提言~」「子どもの貧困と健康~医療者としてどう支援できるのか~」の3つのシンポジウムが開催され、2日間にわたる医療研は終了した。









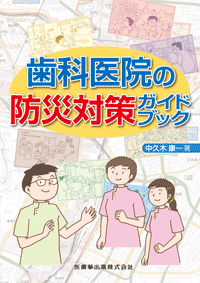 歯科医院の防災対策ガイドブック(医歯薬出版株式会社)
歯科医院の防災対策ガイドブック(医歯薬出版株式会社)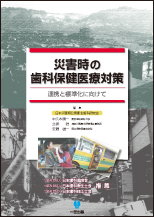 災害時の歯科保健医療対策~連携と標準化に向けて~(一世出版株式会社)
災害時の歯科保健医療対策~連携と標準化に向けて~(一世出版株式会社)