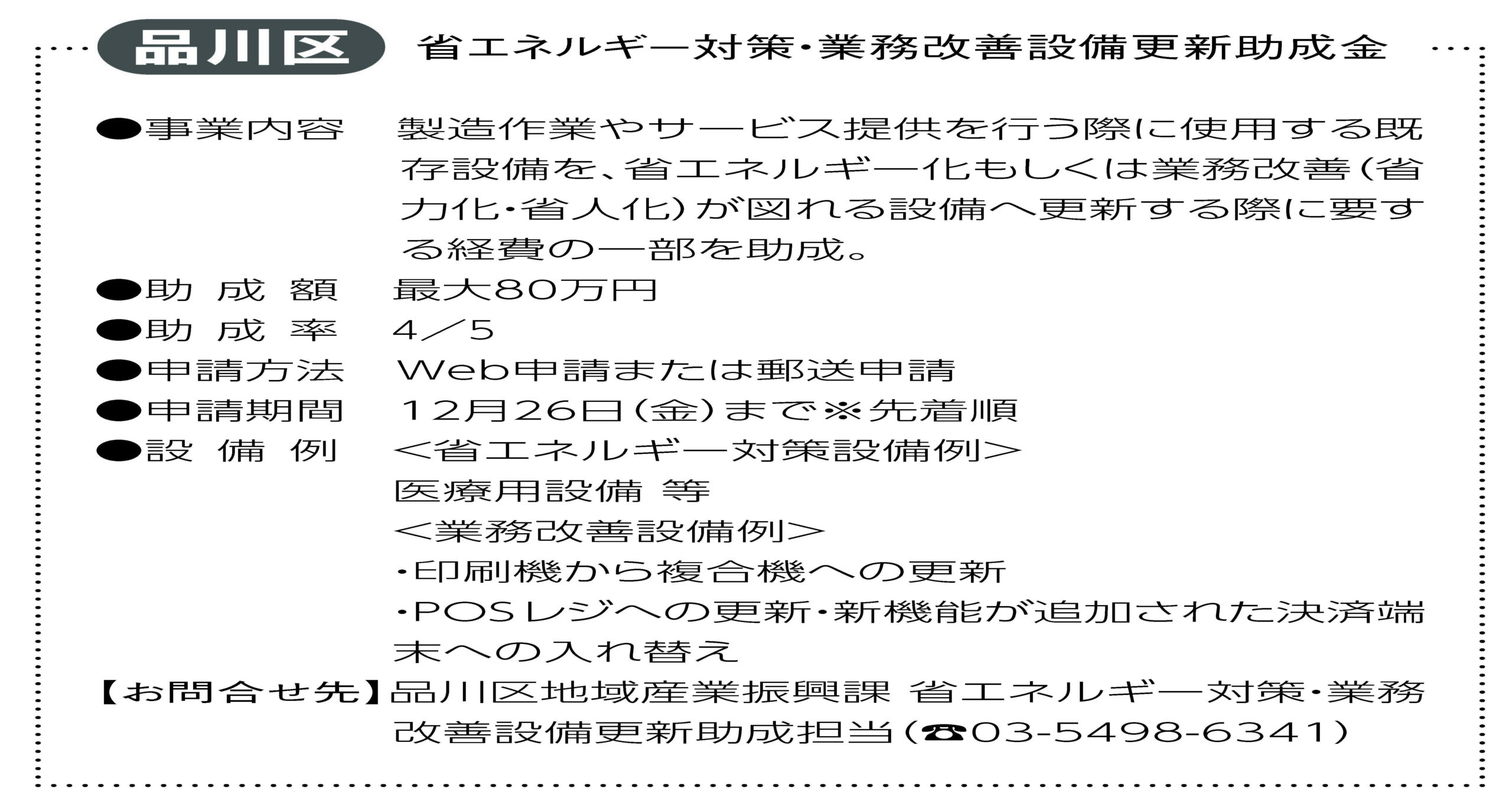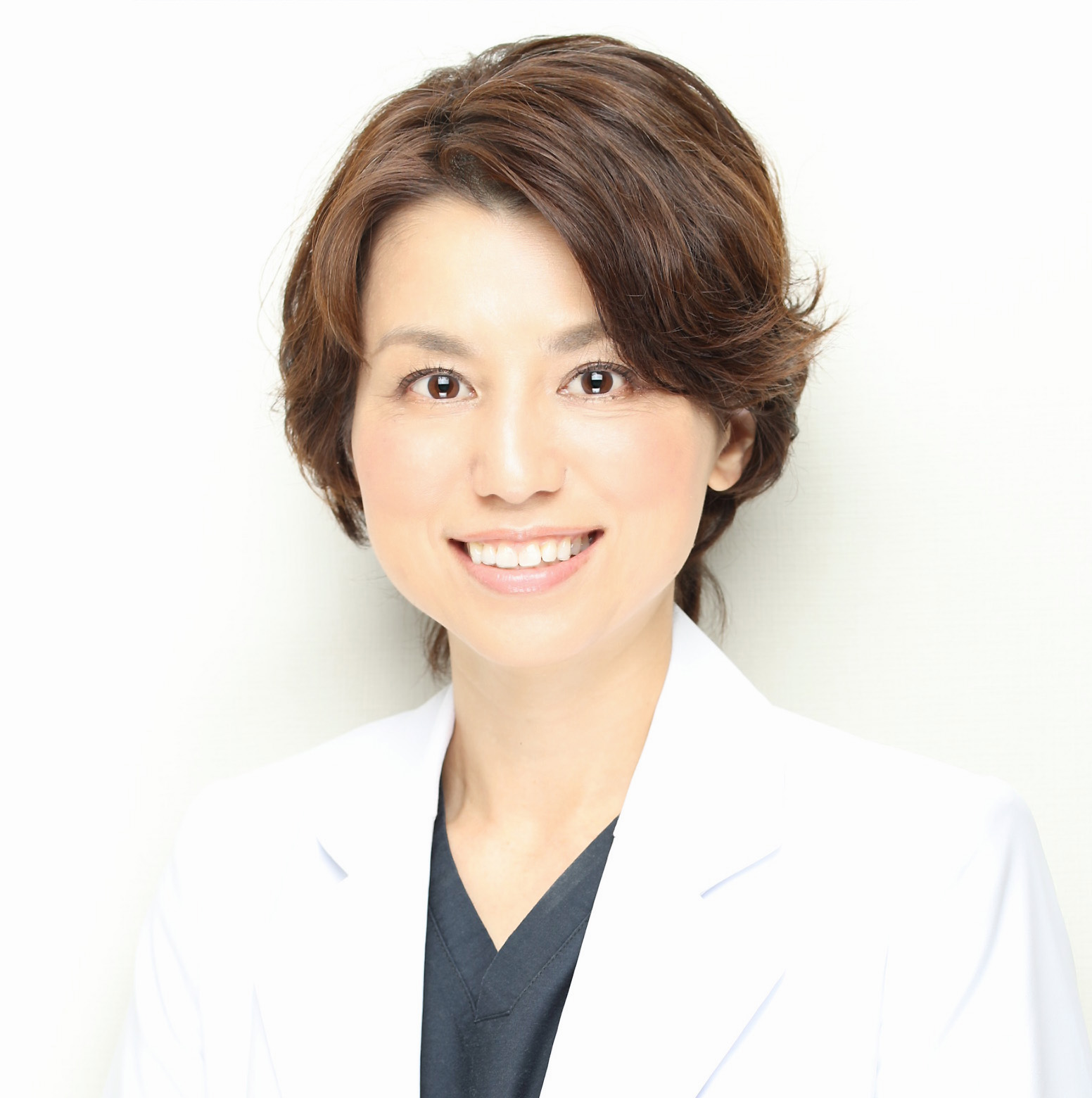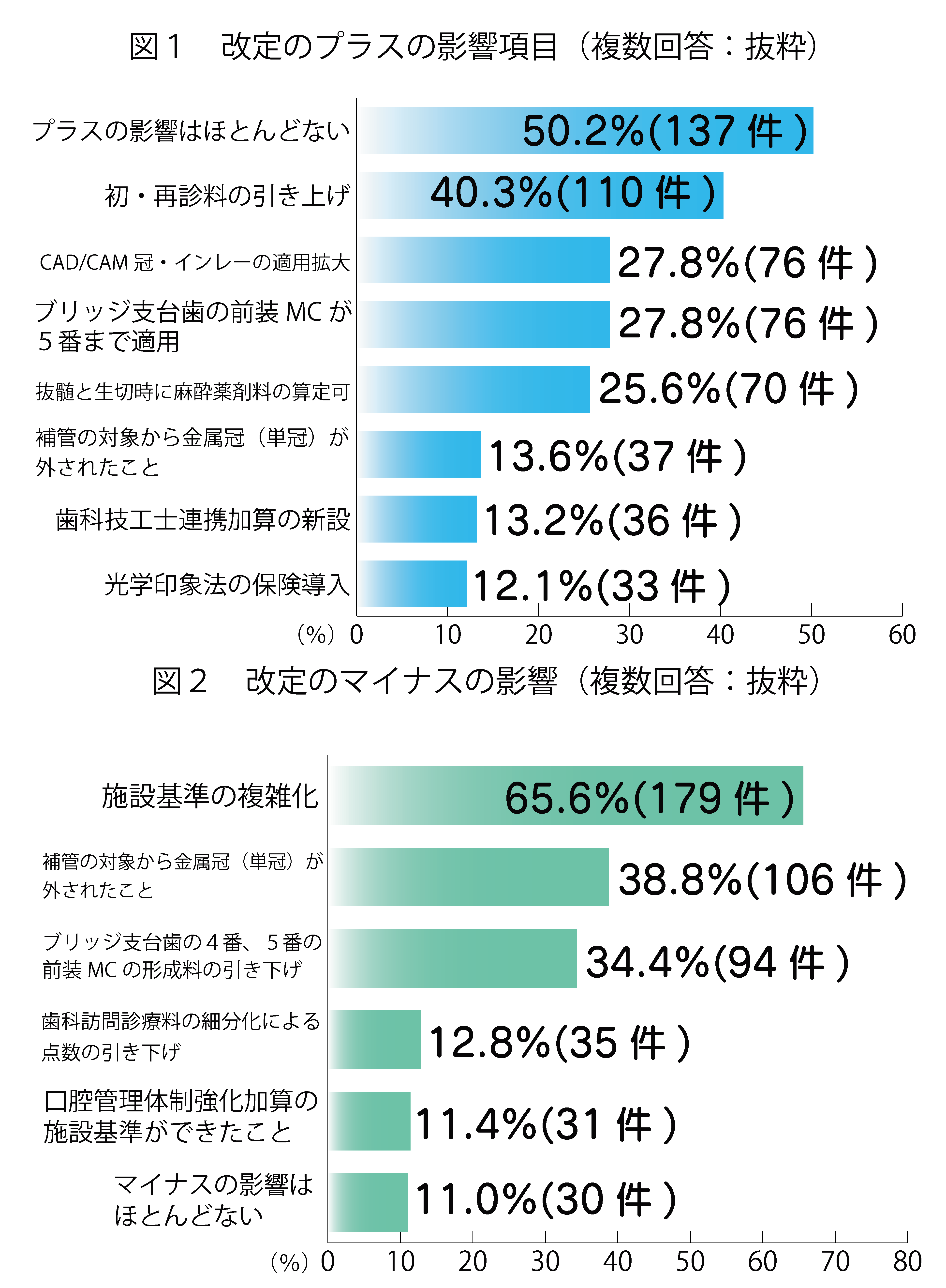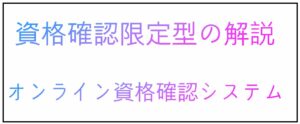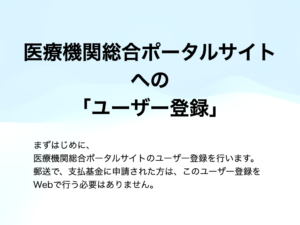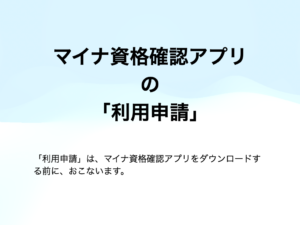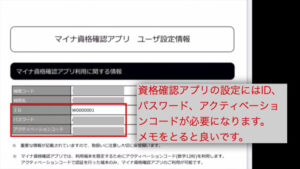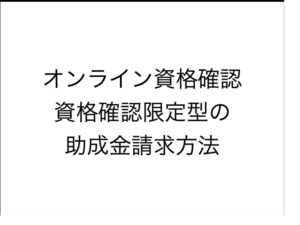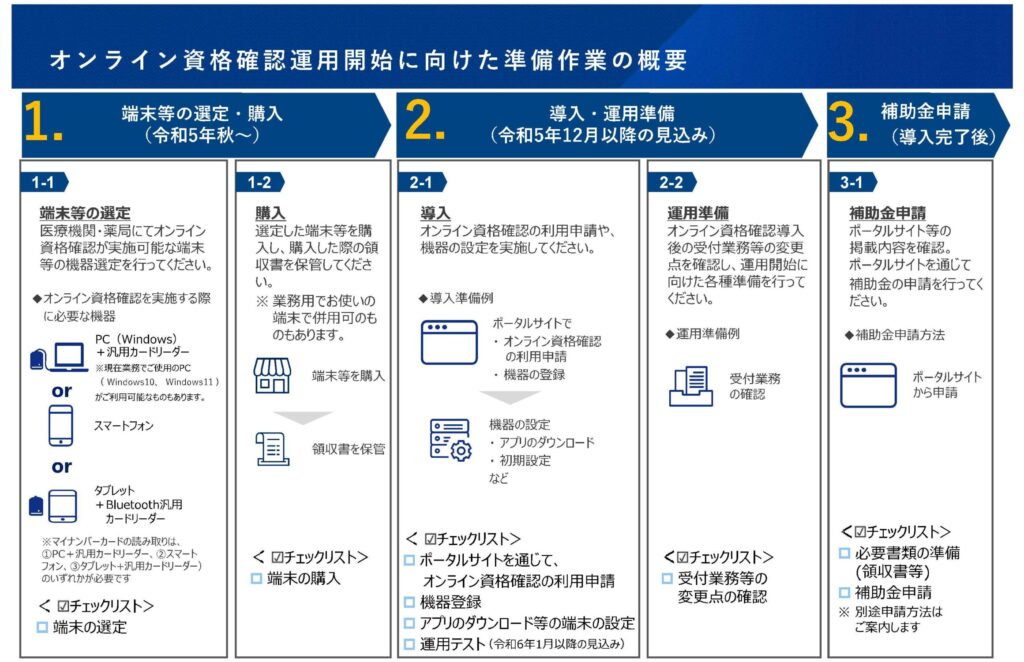*-*-*-*-*-*-*-*
東京都から示されたQ&Aの内容等整理しました。
元のQ&Aはこちら(
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/hokeniryo/2025-07-30-143518-461)からご覧ください。
Q&Aの番号は協会で改めて附番したものです。
<全体>
Q1 交付手続きの流れはどのようになりますか。
Q2 対象施設が申請時等に提出する書類を教えてください。
Q3 いつからいつまでの経費が対象になるのでしょうか。
Q4 国の交付決定前に実施した取組であっても、給付対象になるのでしょうか。
Q5 この支援事業に上限または優先順位などはあるのでしょうか。早く申請した病院から認められるなどは無いでしょうか。
Q6 医療機関から都道府県に支給申請書兼口座振込依頼書を提出する際、法人から、当該法人が運営する複数の施設を取りまとめて申請することは可能でしょうか。
Q7 消費税の仕入控除税額の返還等の処理は必要でしょうか。
Q8 機器の購入や処遇改善を行ったことを証明する書類(領収書等)について、実績報告時に添付する必要はありますか。
Q9 活用意向調査はすでに周知されているのでしょうか。
<ICT機器等の導入による業務効率化関係>
Q10 「ICT機器等の導入による業務効率化」について、タブレット端末、インカム、WEB会議設備等が例示されていますが、それらを利用するためのインフラ(Wi-Fiなど)の整備は対象でしょうか。
Q11 Q10に関連し、患者サービスの向上に資する事業(院内に患者向けWi-Fiを設置するなど)は対象となりますでしょうか。
Q12 Q10に関連し、AI問診等、アプリの導入は対象になりまか。
Q13 事業として実施したいことがあるが、購入する機材について東京都の審査があるという認識で良いか。それとも1床当たりの金額で趣旨に合うものを購入してよいのか。これまでは会議資料は紙を印刷し配布するアナログ方式だが、デジタル化してプレゼンテーション画面で実施したい希望を持っている。
Q14 支給対象となる取組のうち、「ICT機器導入」が支給額に満たない場合は、当該実績額までしか支給されないのでしょうか。
Q15 例えば、「ICT 機器等の導入による業務効率化」に使用することとして18万円を申請して概算で交付を受けた場合、実際には15万円を使用し、残額の3万円を「給付金を活用した更なる賃上げ」(例:一時金)に充てた場合は改めて申請する必要があるのでしょうか。それとも、実績報告時に「ICT機器等の導入による業務効率化」として15万円を使用したことと、「給付金を活用した更なる賃上げ」として3万円を使用したことをそれぞれ報告することで足りるでしょうか。
Q16 「ICT機器等の導入による業務効率化」の取組を検討していますが、機器の導入費用が支給額(基準額)に満たない場合は、どうすればいいでしょうか。
Q17 給付金を「ICT機器等の導入による業務効率化」や「給付金を活用した更なる賃上げ」に充てたことをどのように確認すればよいですか。
Q18 給付金の支給対象となる取組のうち、「ICT機器等の導入による業務効率化」について、具体的にどういった取組が給付対象となるのでしょうか。
Q19 「ICT機器等の導入による業務効率化」について、ICT機器等をリース契約で導入する場合も対象になりますか。
Q20 ICT機器等の導入を行った場合、いつまでに支払・納品を行っている必要がありますか。
<タスクシフト/シェアによる業務効率化関係>
Q21 タスクシフト・シェアによる業務効率化だが、新たに配置したことをどのように厚労省に示すのか?(給与明細の提出とか?)
Q22 給付金の支給対象となる取組のうち、「医師事務作業補助者、看護補助者等の職員の新たな配置によるタスクシフト/シェアによる業務効率化」について、具体的にどういった取組が給付対象となるのでしょうか。
<給付金を活用したさらなる賃上げ関係>
Q23 給付金を活用したさらなる賃上げだが、こちらも実施したことをどのように厚労省に示すのか?
Q24 給付金を活用した更なる賃上げについて対象となる職種を教えてください。
Q25 「更なる賃上げ」の場合、職員に対する「一時給付金の支払い」も対象となるのでしょうか。
Q26 当院は2024年6月にベースアップ評価料を届出し、現在も継続して届出をしており、処遇改善として当院職員へ賃金改善を実施しております。支給要件3項目の何れかに該当すれば補助金該当となるのでしょうか。
Q27 ベースアップ評価料の届け出済みですが、支給要件で「2024年4月1日から2025年3月31日までの間に ~ 処遇改善を図る場合」とあり、年度内に処遇改善が完了していない場合は支給要件を満たさないことになりますか。
Q28 ベースアップ評価料については本事業終了時点においても算定を行っている必要はないでしょうか。
Q29 ベースアップ評価料が届け出られていることをどのように確認すればよいのでしょうか。
Q30 2023年度にすでに賃上げをし、そのまま維持している場合、2024年度も賃上げをしている、という判断をしてよいでしょうか。
Q31 法定福利費等の事業主負担の増加分は、「給付金を活用した更なる賃上げ」の対象となるのでしょうか。
Q32 ベースアップ評価料創設前の2024年4月にベースアップを実施している場合、2024年4月及び5月のベースアップ分(基本給等の増加分)およびベースアップに伴う法定福利費等の事業主負担の増加分は「給付金を活用した更なる賃上げ」の対象となるのでしょうか。
Q33 例えば、3月 31 日までにべースアップ評価料を届け出ている対象施設の開設者が個人でしたが4月1日以降に開設者が法人に変更となる場合等、3月 31 日までにベースアップ評価料を届け出ていた対象施設の開設者が4月1日以降に変更となった場合、支援の対象になるのでしょうか。
ページの先頭に戻る
<全体>
Q1 交付手続きの流れはどのようになりますか。
A1 東京都では、対象件数が多いため申請受付窓口及びコールセンターを開設しています。コールセンターの電話番号 0570-018-085 (平日9時~17時)
目次に戻る
Q2 対象施設が申請時等に提出する書類を教えてください。
A2 東京都の交付申請においては、入力フォーム及び口座情報等を含めた指定様式(内容は同じ)を配布しますので、そちらをご活用ください。
目次に戻る
Q3 いつからいつまでの経費が対象になるのでしょうか。
A3 2024年度~2025年度の取組(2024.4.1~2026.3.31)を対象とする予定です。東京都では、2025年中に交付申請を受付、毎月概算払いすることを検討しています。なお、実績報告についても2025年度中に事務処理ができるよう検討しています。概算で交付した額が交付すべき確定額を上回るときは、その上回る額を返還します。
目次に戻る
Q4 国の交付決定前に実施した取組であっても、給付対象になるのでしょうか。
A4 実施要綱に基づいた事業であれば、2024年4月1日以降に実施した取組は補助対象として扱っていただき差し支えありません。
目次に戻る
Q5 この支援事業に上限または優先順位などはあるのでしょうか。早く申請した病院から認められるなどは無いでしょうか。
A5 対象医療機関等の区分ごとの給付の上限額は決まっています。優先順位や、申請した病院から認められるという仕組みではありません。(申請及び交付スケジュールについては検討中です。)なお、給付の対象となる機器・備品1台の購入価格に上限は定めてられていません。
目次に戻る
Q6 医療機関から都道府県に支給申請書兼口座振込依頼書を提出する際、法人から、当該法人が運営する複数の施設を取りまとめて申請することは可能でしょうか。
A6 東京都では、原則として施設毎の申請を想定しております。訪問看護ステーションについては、他の補助事業と同じように申請できるよう検討しております。
目次に戻る
Q7 消費税の仕入控除税額の返還等の処理は必要でしょうか。
A7 原則として2026年度に仕入控除税額についてのご報告を提出いただくことになります。なお、補助対象経費の全額が仕入控除税額の対象とならない給与や賞与等に当てられている場合は、0円となるものと考えています。
目次に戻る
Q8 機器の購入や処遇改善を行ったことを証明する書類(領収書等)について、実績報告時に添付する必要はありますか。
A8 東京都としては、国のスタンスを考慮し、原則として証拠書類の添付は求めませんが、申請内容の確認に際し、別途提出を求める場合がございますのでご承知おきください。
(国の考え方-執行事務の簡素化を図る観点から、国としては申請時や実績報告時の証拠書類の添付は不要と考えています。また、実績報告は対象施設において給付金を活用した支出額の総額が給付金の対象となる取組に要した費用の総額と一致していることを確認するとともに、各取組に要した費用から政策効果を把握するものであることからも証拠書類の添付は不要と考えています。なお、領収書や賃金台帳等の帳簿等の証拠書類については、補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間は対象施設側で保管させるようにしてください。)
目次に戻る
Q9 活用意向調査はすでに周知されているのでしょうか。
A9 活用意向調査は現時点で実施しておらず、予定もありません。本事業の活用をご希望の場合には、2025年3月31日(月)までに、関東信越厚生局にベースアップ評価料を届け出ていただく必要があります。
目次に戻る
<ICT機器等の導入による業務効率化関係>
Q10 「ICT機器等の導入による業務効率化」について、タブレット端末、インカム、WEB会議設備等が例示されていますが、それらを利用するためのインフラ(Wi-Fiなど)の整備は対象でしょうか。
A10 対象になります。利用料については対象期間分に按分するなど、申請金額の算出時はご留意ください。
目次に戻る
Q11 Q10に関連し、患者サービスの向上に資する事業(院内に患者向けWi-Fiを設置するなど)は対象となりますでしょうか。
A11 本事業は、人材確保が喫緊の課題となっている中で、限られた人員でより効率的に業務を行う環境の整備費用に相当する金額を、給付金として支給することにより、業務の生産性を向上させ、職員の処遇改善につなげることを目的としており、ご質問の場合は対象外と考えます。
目次に戻る
Q12 Q10に関連し、AI問診等、アプリの導入は対象になりまか。
A12 対象になります。
目次に戻る
Q13 事業として実施したいことがあるが、購入する機材について東京都の審査があるという認識で良いか。それとも1床当たりの金額で趣旨に合うものを購入してよいのか。これまでは会議資料は紙を印刷し配布するアナログ方式だが、デジタル化してプレゼンテーション画面で実施したい希望を持っている。
A13 「ICT機器等の導入による業務効率化」について、導入により施設内の業務効率化に資するICT機器等が給付の対象となります。また、ICT機器以外の機器、あるいはソフトウェアなどについても、導入により施設内の業務効率化に資することが認められるものであれば給付の対象となり得ます。ご提出いただくのは、厚労省の定める別紙様式1及び2(生産性向上・職場環境整備等支援事業申請書・実績報告書)の内容となり、東京都の審査はこの事業の目的に合致する機器であるかを確認するものです。(様式の記入欄に導入目的も記載いただくとわかりやすいものと考えます。)
目次に戻る
Q14 支給対象となる取組のうち、「ICT機器導入」が支給額に満たない場合は、当該実績額までしか支給されないのでしょうか。
A14 「ICT機器導入」のみで基準額を満たす必要はなく、複数区分を組み合わせた金額について、基準額の範囲内で交付決定、給付となります。
目次に戻る
Q15 例えば、「ICT 機器等の導入による業務効率化」に使用することとして18万円を申請して概算で交付を受けた場合、実際には15万円を使用し、残額の3万円を「給付金を活用した更なる賃上げ」(例:一時金)に充てた場合は改めて申請する必要があるのでしょうか。それとも、実績報告時に「ICT機器等の導入による業務効率化」として15万円を使用したことと、「給付金を活用した更なる賃上げ」として3万円を使用したことをそれぞれ報告することで足りるでしょうか。
A15 国としては、実績報告時に報告いただくことで足りると考えています。
目次に戻る
Q16 「ICT機器等の導入による業務効率化」の取組を検討していますが、機器の導入費用が支給額(基準額)に満たない場合は、どうすればいいでしょうか。
A16 実際の費用が支給額(基準額)を下回る場合はその差額を返還することとなりますが、事業の目的を踏まえ、「給付金を活用した更なる賃上げ」による職員への一時金の支給などにより、支給額(基準額)以上の取組となるようご検討ください。
目次に戻る
Q17 給付金を「ICT機器等の導入による業務効率化」や「給付金を活用した更なる賃上げ」に充てたことをどのように確認すればよいですか。
A17 早期に医療機関の経営を支援する必要があるため、執行事務の簡素化を図る観点から簡潔な申請手続きをお願いしており、申請額について個別にご確認いただくことは想定していません。なお、会計検査院や出納当局から必要に応じて証拠書類の提出が求められれば、対象施設にはいつでも提出できるよう保管してください。
目次に戻る
Q18 給付金の支給対象となる取組のうち、「ICT機器等の導入による業務効率化」について、具体的にどういった取組が給付対象となるのでしょうか。
A18 導入により施設内の業務効率化に資するICT機器等が給付の対象となります。例えば、タブレット端末、離床センサー、インカム、WEB会議設備、床ふきロボット、監視カメラなどの機器が想定されますが、これらの機器以外にも、施設内の業務効率化に資するもの(例:マイナンバーカードのカードリーダー、業務効率化に資する医療機器やロボット等)であれば幅広く対象となり得ます。また、ICT機器以外の機器、あるいはソフトウェアなどについても、導入により施設内の業務効率化に資することが認められるものであれば給付の対象となり得ます。
目次に戻る
Q19 「ICT機器等の導入による業務効率化」について、ICT機器等をリース契約で導入する場合も対象になりますか。
A19 事業の対象期間内に生じる金額については対象になり得ます。
目次に戻る
Q20 ICT機器等の導入を行った場合、いつまでに支払・納品を行っている必要がありますか。
A20 概算で医療機関に交付している場合は、出納整理期間中までに医療機関において支払を終えていれば問題ありませんが、納品は補助対象期間内に終えている必要があります。
目次に戻る
<タスクシフト/シェアによる業務効率化関係>
Q21 タスクシフト・シェアによる業務効率化だが、新たに配置したことをどのように厚労省に示すのか?(給与明細の提出とか?)
A21 ご提出いただくのは、厚労省の定める別紙様式1及び2(生産性向上・職場環境整備等支援事業申請書・実績報告書)の内容となります。雇用契約書や給与明細等の証拠書類について、添付は求められていませんが、補助金の額の確定の日の属する年度の終了後5年間保管してください。
目次に戻る
Q22 給付金の支給対象となる取組のうち、「医師事務作業補助者、看護補助者等の職員の新たな配置によるタスクシフト/シェアによる業務効率化」について、具体的にどういった取組が給付対象となるのでしょうか。
A22 既に雇用している医師や看護師等の職員の負担軽減のために、新たに医師事務作業補助者や看護補助者などの職員を雇用する際の人件費が対象となります。また、従前から勤務している職員が、新たに医師や看護師等の職員の負担軽減に資する業務に配置された場合の人件費や人材派遣・業務委託の経費も対象となり得ます。
目次に戻る
<給付金を活用したさらなる賃上げ関係>
Q23 給付金を活用したさらなる賃上げだが、こちらも実施したことをどのように厚労省に示すのか?
A23 (A21に同じ)
目次に戻る
Q24 給付金を活用した更なる賃上げについて対象となる職種を教えてください。
A24 薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、看護補助者、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、歯科業務補助者、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、保育士、救急救命士、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゆう師、柔道整復師、公認心理師、診療情報管理士、医師事務作業補助者、事務職員、その他医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。ただし、40歳未満の若手医師・若手歯科医師はその限りではない。)に充てることができます。
目次に戻る
Q25 「更なる賃上げ」の場合、職員に対する「一時給付金の支払い」も対象となるのでしょうか。
A25 一時給付金の支払いも対象となります。ただし、ベースアップ評価料による賃上げを「給付金を活用した更なる賃上げ」とは見なせません。本給付金を活用して更なる賃上げを行う場合は、既に雇用している職員について、ベースアップ評価料で手当されている部分とは別にベースアップ・手当・一時金のいずれかにより 賃上げを行う取組が対象となるため、医療機関の持ち出しによって、ベースアップ評価料による収入以上にベースアップ分として支出している部分に対して充当することは可能です。なお、単に職員の人件費の基本給部分や定期昇給部分に充当し、上記のベースアップ・手当・一時金などの形で還元されない場合は、給付対象外です。
目次に戻る
Q26 当院は2024年6月にベースアップ評価料を届出し、現在も継続して届出をしており、処遇改善として当院職員へ賃金改善を実施しております。支給要件3項目の何れかに該当すれば補助金該当となるのでしょうか。
A26 1つの区分のみで基準額を満たす必要はなく、複数区分を組み合わせた金額について、基準額の範囲内で交付決定、給付となります。
目次に戻る
Q27 ベースアップ評価料の届け出済みですが、支給要件で「2024年4月1日から2025年3月31日までの間に ~ 処遇改善を図る場合」とあり、年度内に処遇改善が完了していない場合は支給要件を満たさないことになりますか。
A27 算定を支給要件とされてはいませんが、職員の処遇改善につなげることを目的としている事業趣旨に鑑み、可能な限り算定を行っていただくようお願いします。
目次に戻る
Q28 ベースアップ評価料については本事業終了時点においても算定を行っている必要はないでしょうか。
A28 補助金の交付決定に際し、状況を確認させていただく場合がございますのでご承知おきください。
(国の考え方-算定を支給要件とはしませんが、職員の処遇改善につなげることを目的としている事業趣旨に鑑み、可能な限り算定を行っていただくようお願いします。)
目次に戻る
Q29 ベースアップ評価料が届け出られていることをどのように確認すればよいのでしょうか。
A29 様式記載内容について、関東信越厚生局のホームページにアップロードされている届出状況(参考:
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/chousa/kijyun.html)と一致することを確認いたします。
目次に戻る
Q30 2023年度にすでに賃上げをし、そのまま維持している場合、2024年度も賃上げをしている、という判断をしてよいでしょうか。
A30 2023年度の取組は対象となりません。
目次に戻る
Q31 法定福利費等の事業主負担の増加分は、「給付金を活用した更なる賃上げ」の対象となるのでしょうか。また、ベースアップ評価料の取り扱い時と同様に事業主負担分を一律に 16.5%として扱ってもよいでしょうか。
A31 単なる法定福利費等の増額分の支払は、対象となる取組には含まれませんが、ベースアップ・手当・一時金のいずれかにより賃上げを行う取組に伴い生じる法定福利費等の事業主負担の増加分に充てることは可能です。また、給付額の 83.5%を「更なる賃上げ分」として充てつつ、残り16.5%を当該賃上げ分に附随する法定福利費として充てることは差し支えありません。
目次に戻る
Q32 ベースアップ評価料創設前の2024年4月にベースアップを実施している場合、2024年4月及び5月のベースアップ分(基本給等の増加分)およびベースアップに伴う法定福利費等の事業主負担の増加分は「給付金を活用した更なる賃上げ」の対象となるのでしょうか。
A32 Q24の回答に掲げる職種にかかる増加分であれば対象になり得ます。
目次に戻る
Q33 例えば、3月 31 日までにべースアップ評価料を届け出ている対象施設の開設者が個人でしたが4月1日以降に開設者が法人に変更となる場合等、3月 31 日までにベースアップ評価料を届け出ていた対象施設の開設者が4月1日以降に変更となった場合、支援の対象になるのでしょうか。
A33 ○ 例示の場合は実質的には同じ対象施設となるため、対象になり得ます。
○ また、3月 31 日までにベースアップ評価料を届け出ていた対象施設が事業譲渡等によって4月1日以降開設者が変更となった場合も、地域で果たしている役割や機能が実質的に同じと都道府県において判断できるのであれば、対象になり得ます。
目次に戻る
※ 上記内容は2025年7月7日現在の情報を協会がまとめたものです。
ページの先頭に戻る