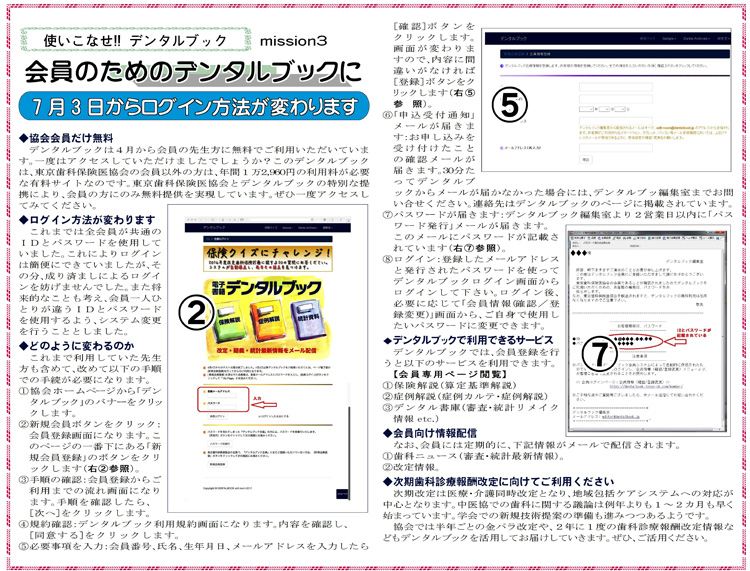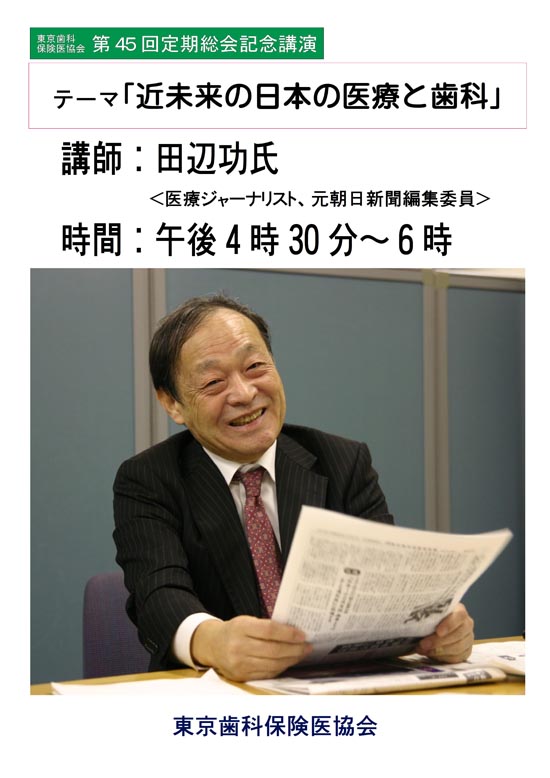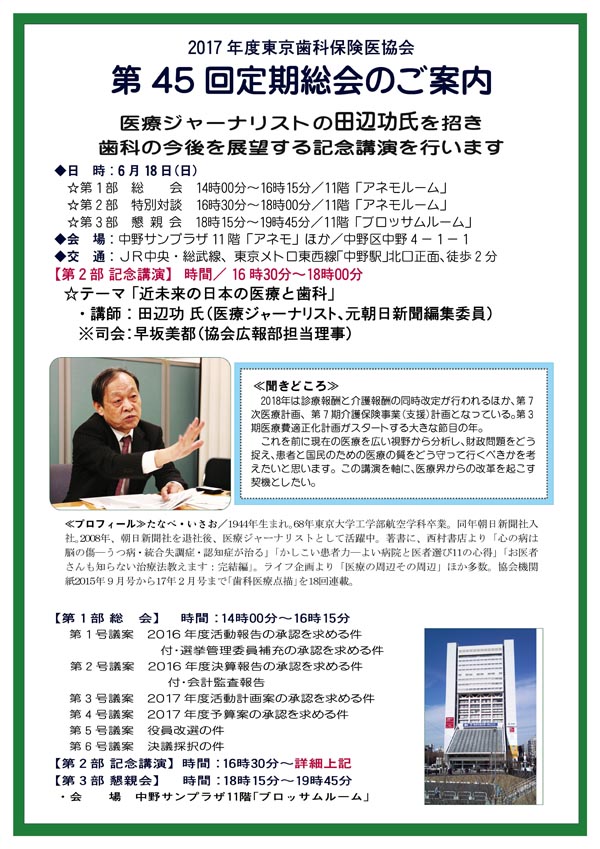政策委員長主張「需給問題が歯科医師の質の低下に」
本年3月、「第110回歯科医師国家試験」の合格発表があり、新たに1983名の歯科医師が誕生した。
今回の合格率は、全体で65.0%となり、第106回が71.2%で、第107回から第109回までの3年間が63%台であったので久しぶりのアップであった。
◆歯科医師国試合格者数4年連続2000人前後の背景は
一方、合格者数は4年連続2000人前後である。推測ではあるが、直近4年間は合格者数を2000人程度とすることが、初めから決められていたのではないだろうか。来年以降も合格者数に注目していく必要がある。推測が正しければ、合格率は受験者数によって微増減した数字になっているだけで、大きな意味を持たないこととなる。また、過去は資格試験の意味合いが強かった歯科医師国家試験が、近年では競争原理が働く選抜試験の様相を呈している。そのため、大学によっては国家試験の合格率を上げることに注力し、人格的に良質な資質を有する歯科医師を育成する本来の歯学教育の目的が疎かになってはいないだろうか。
◆増加する卒業認定のみ人数と今後
新卒において、出願者数2462人、受験者数1855人、合格者数1426人の結果、不合格者数は429人であった。なお、出願者数と受験者数の差は607人で、前年11月に出願したが、留年、卒業延期、そして国家試験は受験できず卒業認定のみとなった方たちの総数で、その数は年々増加している。特に、いくつかの私立大学で卒業認定日を操作することによって、国家試験を受験することはできないが、卒業はさせるということで、合格率の粉飾を図る戦略を行っていることが疑われる。これらの方たちは、次の第111回では新卒に分類されると考えられ、先送りにしただけに過ぎない。学生を大学から卒業させたということは、間接的に歯科医師国家試験を受験できる知識や技術などを身につけたと判断したことである。したがって、卒業認定のみを行うことは、大学自体が学生の最終目標である歯科医師免許取得のための教育を放棄し、卒業後は免許取得のため、各自で国家試験の勉強をせよと通告したこととなり、責任の所在に大いに疑問がある。
2016年度の29大学歯学部・歯科大学の入学定員数は2449人である。合格者数が2000人前後の現状からみると、前提としての入学定員数が多すぎるのではないだろうか。厚生労働省(以下、「厚労省」)は過去、歯科医師の需給に関して議論を行い、大学の入学・募集定員について数回の提言が出されている。その結果、各大学が取り組み、すでに削減が行われているが、十分なのであろうか。
「第110回歯科医師国家試験」での既卒の受験者数は1094人で不合格者数は637人である。厚労省サイドでは、以前から受験回数制限の議論が行われており、将来的に受験回数が制限される可能性があるが、現時点では、いわゆる国家試験浪人の方たちも多くの方が諦めることはないと思われる。したがって、入学定員数が維持され、2000人の合格者数を続けるならば、大学を卒業しても歯科医師になれない方たちが増え続けることとなる。このことは歯科界のみならず、社会的な問題といっても過言ではない。
◆学生の質か教育内容の差か
一方、最低修業年限の歯科医師国家試験合格率からみると、2010年4月入学者が六年間の教育を受け、2016年3月の「第109回歯科医師国家試験」に合格した比率は、29大学歯学部・歯科大学で平均50.7%、17私立大学に限ると平均42.7%である。全体でも半数の学生が留年や退学などの理由により、いわゆるストレートで歯科医師免許を取得していない。また、私立大学では、最高74.2%から最低13.2%までと、大学間での差が大きい。この原因は、そもそも学生側の質に問題があるのか、医育機関である各大学の教員や教育内容に差があるためか、証左がないため判らず断定できない。しかし、この格差は異常な状態といわれても致し方ない数字である。
◆歯科医療費の総枠拡大と歯科医師の将来の量的供給そして「質」
2014年の歯科医師総数は10万3972人、そのうち医療施設従事者数は10万965人で、人口10万対歯科医師数は81.8人である(厚生労働省「医科・歯科医師・薬剤師調査」)。1970年の人口10万対歯科医師数が35.2人であったので、大幅に増加しているといえる。しかし、世界的にみるとこの数字は多いほうとはいえない。また、歯科医療サービス提供体制の充実のためにさらに歯科医師を増やす必要があるという論理にはなるが、国民皆保険を堅持する立場からいえば、歯科医師が増えれば歯科医療費の総枠拡大が不可避となる。政府が社会保障費の削減を推し進めている現状では、その論理に同意することは困難である。
総人口の減少、あるいは疾病の軽症化などを背景に考えると、現在の歯科医療を持続することだけを進めるならば、歯科医師の需要予測としては厳しい。したがって、将来的に予防や継続管理の充実、在宅歯科医療などにシフトしていかなくてはならない。
このことは、2016年診療報酬改定で「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」も新設、SPTの要件緩和、初期う蝕への評価など、厚労省はすでに動き出している。しかし、変化する歯科的ニーズに対して歯科医療が良好にシフトチェンジできたとしても、将来的な量的供給は今後も現状維持できるのであろうか。
他方、重要なこととして需給問題は歯科医師の質と密接な関係がある。職業として歯科医師を選択する人が減少していることは、私立大学歯学部・歯科大学の競争倍率の低下や大学予備校の発表している偏差値の数値に現れている。入学定員が充足していない大学、また偏差値をインターネットで調べると、46以下とされている大学が複数あるのは厳然たる事実である。
◆協会は新規参入1200名を提言
6年間という長い期間、さらに6年間で卒業できるとは限らず、歯科医師国家試験のハードルも高く、何年も浪人しても歯科医師になれない可能性は現実的にありうる。また、歯科医師になっても「ワーキングプア」が少なくないとメディアから喧伝され、必ずしもイメージがいいとはいえない。私立大学ならば、かかる学費も決して安くない。それらの背景があり、歯科医師を目指す高校生、受験生が多くはないのが、残念ながら現状といえる。
歯科医師全体の質の低下は国民のためにならないことは間違いない。総合的に考えると抜本的な解決のためには、歯科医師の需給から考えることが現実的ではないだろうか。
東京歯科保険医協会は、2010年に発表した「21世紀にふさわしい歯科改革提言」の中で「歯学部の統廃合をすすめ地域偏在をなくし、歯科医師の新規参入は1200名に削減すること」と提言している。急激な変化を望むわけではないが、入り口を制限しても、早くても結果が出るのは6年、研修医期間を考えると7年かかる。大学の所管は文部科学省であり、厚労省と協同して速やかに対策を講じる必要がある。今回、将来の歯科界を危惧し、あえて主張させていただいた。
2017年6月1日
東京歯科保険医協会
政策委員長 坪田有史