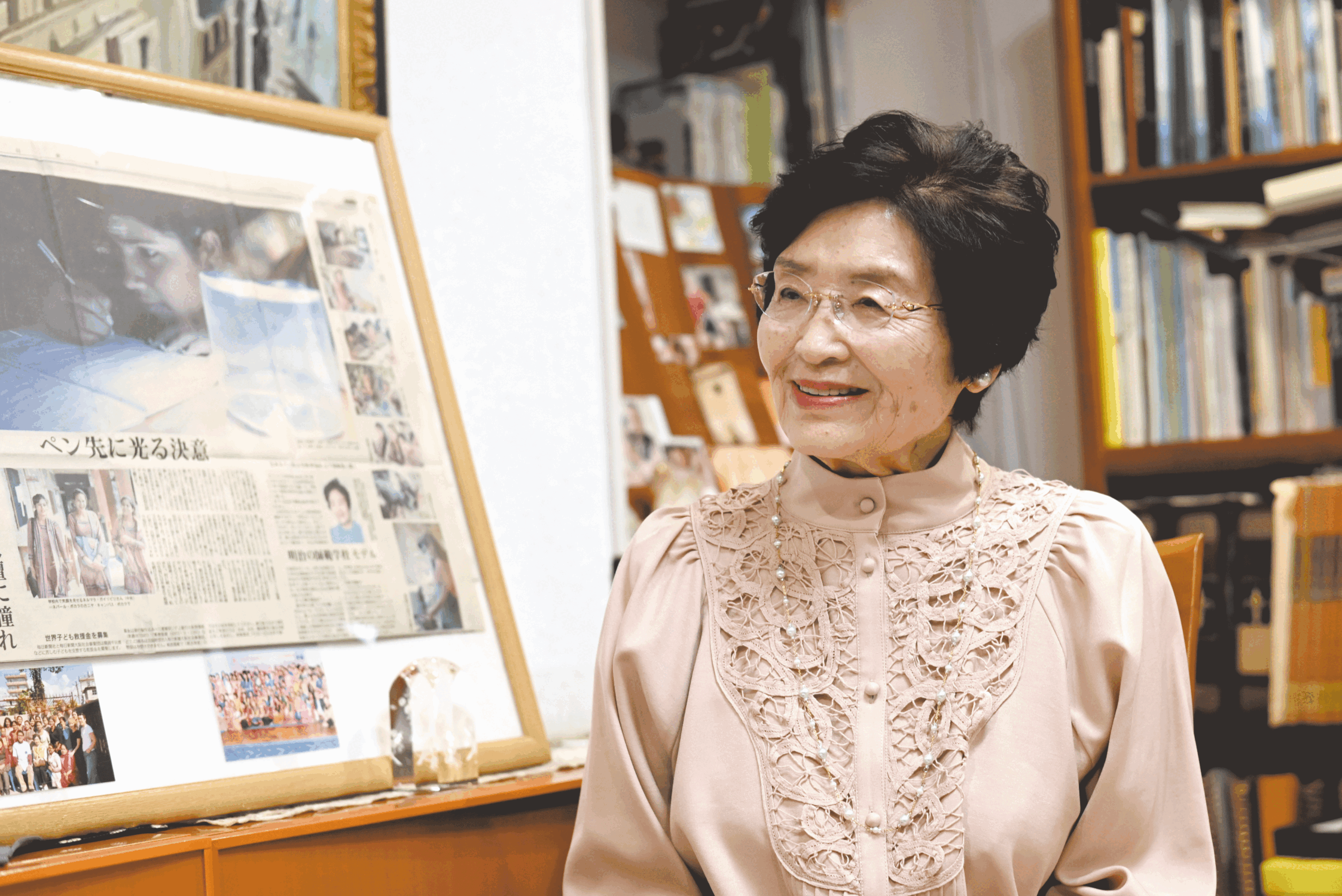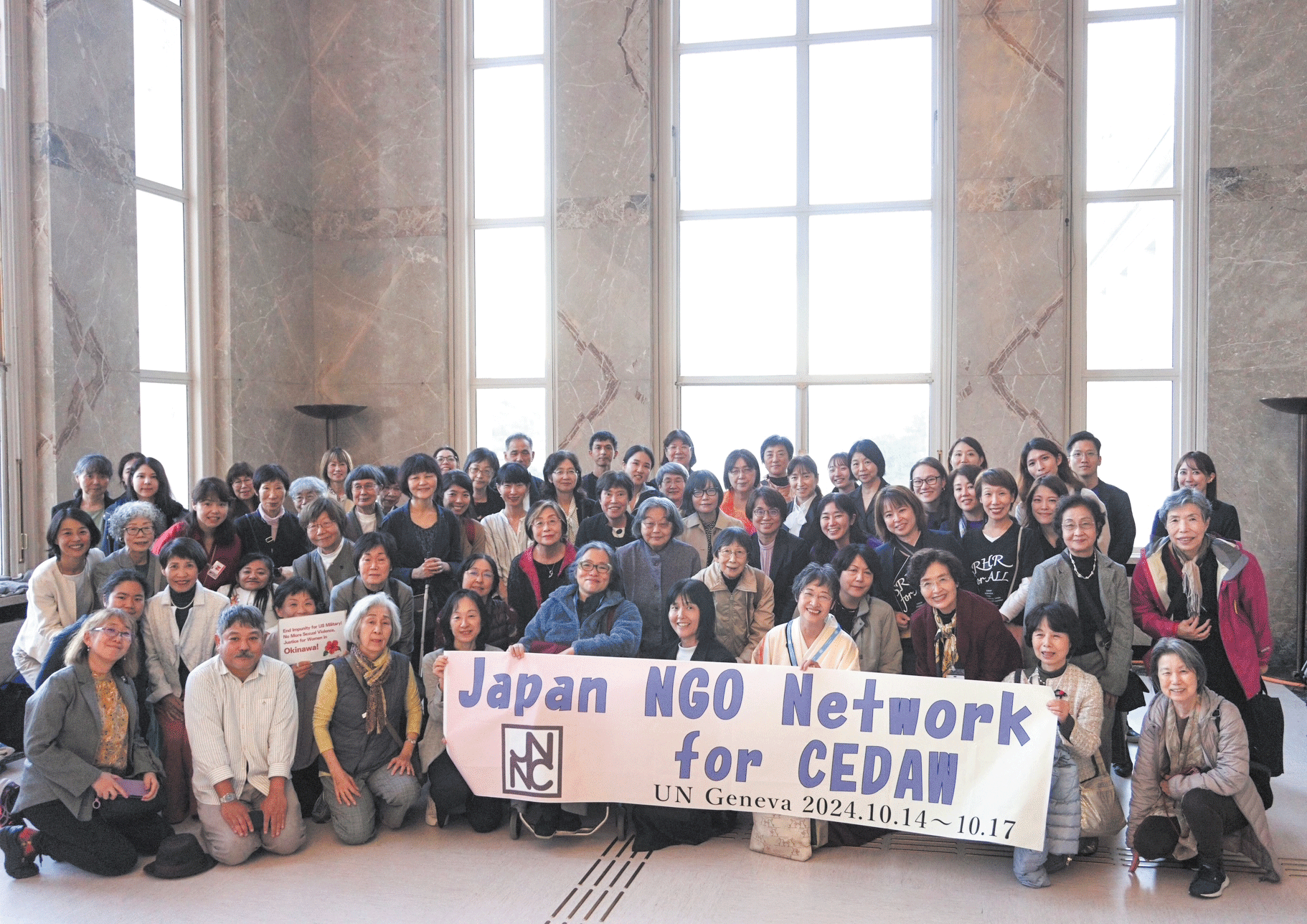【インタビュー】低迷する日本のジェンダーギャップ解消へ 「根本的に転換できる」(前編)/山下 泰子氏(文京学院大学名誉教授・法学博士)
「戦後民主主義教育の洗礼を受けた」―。戦中・戦後と歴史的な社会の変化とともに幼少期を過ごす中で、自らの人権意識が醸成されたと語る文京学院大学・山下泰子名誉教授(86歳)。社会に出た時の経験をきっかけに、ジェンダー法の道を歩むようになり、現在も女性差別撤廃条約の選択議定書批准を目指し、精力的に活動する。2回にわたり、日本のジェンダー問題や課題解決に向けた取り組みについて聞いた。聞き手は、協会の早坂美都副会長。
―ご自身の生い立ちやジェンダー問題に関心をもったきっかけを教えてください。
1945年に国民学校に入学し、終戦を迎えた8月15日を境に教科書を墨塗りして使うようになり、小学生ながらに価値観の転換を体感しました。1947年に日本国憲法が施行され、基本的人権や男女平等についてしっかり学びました。そんな中、中央大学法学部を卒業しても、4年制大卒の女性の就職は厳しく、ようやく採用された貿易会社も、社員教育から男女差別がありました。毎日、お茶くみと社長のお昼のお運びに明け暮れて、1年で退職。大学院に戻って国際人権法を学ぶことにしました。
―社会の変遷やご自身の原体験が今の活動に通じているのですね。その後はどのような歩みを。
1979年に国連で女性差別撤廃条約が採択されたのを機に、条約に関する研究を始めました。1985年5月、国会で女性差別撤廃条約批准案件の審議中に、国際法学会で「女子性差別撤廃条約における男女平等」を報告。同年7月、ケニアのナイロビで開催された第3回世界女性会議NGOフォーラムに参加し、圧倒的な女性たちのエネルギーに接し、「女性の力が社会を変える」と確信したことから、女性差別撤廃条約を研究テーマに決めました。振り返ると、人生のターニングポイントで社会的な矛盾を感じたことが、私を女性差別撤廃条約の研究に向かわせたのだと思います。
―改めてジェンダーについて教えてください。
ジェンダーとは、「生物学的な性・セックス(sex)」に対する、「社会的・文化的に構築された性別(gender)」とされています。ジェンダーの概念は、日常生活の中に組み込まれ、考え方や振る舞い方の中に潜む性差別=男性優位の考え方を形成し、家父長制の基盤となっているものだと考えます。しかし、これは人間が生み出したものなので、根本的に転換できるはずです。国際社会におけるジェンダー平等に向けた取り組みの加速に反して、日本は取り残され、世界経済フォーラムの「Global Gender Gap Report」2024年版で、世界146カ国中118位と低迷しています。
―日本の課題はどこに。
2024年10月、日本における女性差別撤廃条約の実施状況の審議が、国連女性差別撤廃委員会(CEDAW、於ジュネーブ)で行われました。その結果、60項目の「総括所見」が日本政府に示されました。総括所見には、2年以内に勧告を実施するための措置を取り、CEDAWに報告しなければならない項目が4つあります。
1つ目は、選択的夫婦別姓の導入。夫婦の姓については、総括所見で民法の改正を要請されるのが今回で4回目です。1996年には、法制審議会の改正要綱までできていますが、それからでも29年が経過しており、対応が遅すぎます。約95%もの女性が旧姓を失って困難に直面している事実に向き合うべきです。
2つ目は、暫定的特別措置として女性の立候補時の供託金の減額。ずばり「女性が国会議員に立候補するために必要な300万円の供託金を減額すること」を勧告しています。
3つ目は、緊急避妊を含む安価で近代的避妊法へのアクセス。16、17歳の少女が避妊薬を入手するために親の同意を得るという要件を撤廃することを含め、すべての女性と少女に、緊急避妊薬を含む安価な近代的避妊法への適切なアクセスを提供することを勧告しています。中絶の方法にも問題があります。
4つ目は、妊娠中絶における配偶者の同意要件の削除。世界203カ国・地域のうち、配偶者の同意が法的要件とされているのは、日本ほか11カ国のみ、G7では日本のみです。国際基準から遅れている日本の状況を変えなければなりません。
―女性差別撤廃条約に関する運動の展開を。
これまでに「女性の権利を国際基準に」という点を念頭にNGO団体を3つ設立しました。まず1997年設立の「国際女性の地位協会」。条約の研究・普及を目指して条文のコンメンタール(法律文書に対する注釈書)2冊とその英訳他、研究成果の出版、年報の発行、シンポジウムの開催などを通じ、国際的な動向を周知するよう努めてきました。2つ目は2002年に結成した「日本女性差別撤廃条約NGOネットワーク」。CEDAWにNGOレポートを提出し、日本の実施状況についての審議がある時には、ニューヨークやジュネーブに傍聴に行き、その結果の総括所見を政府が実行しているかをウォッチし、評価表を作成してCEDAWに提出するなど、差別を受けている女性とCEDAWをつなぐ役割を担っています。3つ目は2019年結成の「女性差別撤廃条約実現アクション」で、「選択議定書の批准」をシングルイシューにしています。日本が女性差別撤廃条約を批准してから40年経過しますが、条約の実効性を高めるための「選択議定書」は批准していません。批准により「個人通報制度」「調査制度」が有効になります。条約上の権利が侵害されて、最高裁まで行っても救済されない場合には、個人通報制度を利用して、直接、個人がCEDAWに申し立てをすることができるようになります。CEDAWは裁判所ではないので、出される「見解」(勧告)に法的拘束力はありませんが、各国政府によって65%ほどは実行されています。
―日本が長らく選択議定書に批准しないのはなぜでしょうか。
最大の要因は、ポリティカル・ウィル(政治的意思)がないことです。2024年10月のCEDAWでの日本報告審議の際、選択議定書の批准について、日本政府の対応状況やタイムライン(見通し)について尋ねられた外務省の担当者は、「23回にわたり、個人通報制度関係省庁研究会を開催するとともに、諸外国における個人通報制度の導入前の準備や準備の実態などについて調査などを行っています。(中略)引き続き政府として各方面から寄せられる意見を踏まえつつ、早期締結について真剣に検討してまいりたいと考えてございます」と回答しました。ここ数年の国会答弁とまったく変わらず、NGO席から失笑が漏れました。タイムラインについては、2020年の事前質問事項で聞かれているのに、4年経っても進展がなく、真剣に検討しているとはいえません。
(後編へ続く)
Profile
やました・やすこ/東京都生まれ。法学博士、文京学院大学名誉教授、ジェンダー法学会元理事長。国際女性の地位協会名誉会長、日本ネパール女性教育協会理事長、男女共同参画社会づくり功労者内閣総理大臣表彰(2015)、外務大臣表彰(2017)。