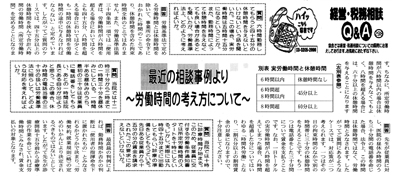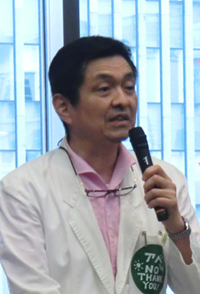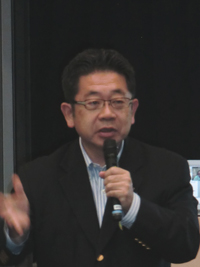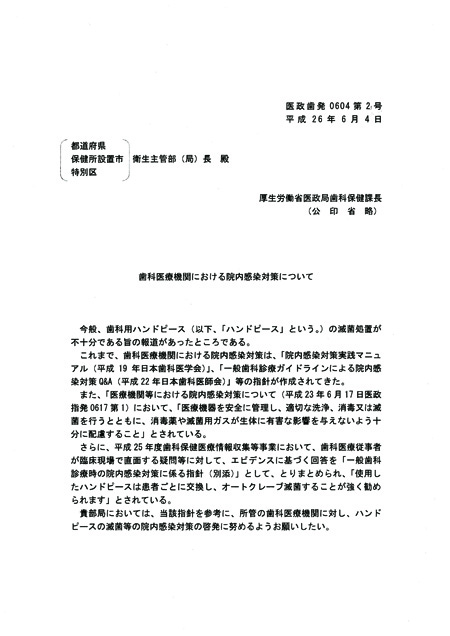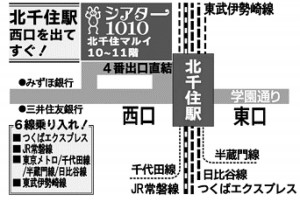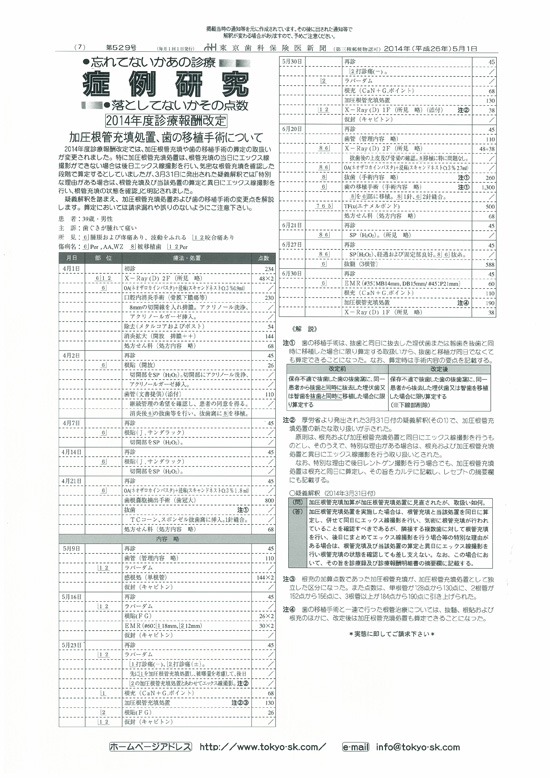「有給休暇の 計画的付与の活用について」/機関紙2014年7月1日(532号)より
質問 当院ではスタッフが2人しかいない。ところが、2人が同じ日に有給休暇を取りたいといってきた。2人で同時に休まれたら困ってしまう。どうすれ ばよいか。
回答 有給休暇は従業員の請求する時季に付与するのが原則ですが、「事業の正常な運営を妨げる場合においては他の時季にあたえることができる」と定めています(労働基準法第三十九条四項)。ご質問のケースでは、スタッフが二人とも休まれては医院の「正常な運営」は確保できないと考えられ、他の時季に取得することを求めても問題はないと考えられます。なお、代替勤務者がいる場合は、必ずしもこうした対応が適切とはいえないこともあります(弘前電報電話局事件<CODE NUMTYPE=UG NUM=9310>最二判昭六十二・七・十)。いずれにせよ、有給休暇の付与はトラブルになりやすい問題ですので、双方がよく話し合うことが肝要です。
質問 フルタイムの従業員に有給休暇を十日以上与えた上に、お盆休みと年末年始の休みを与えたら、当院のような小さな医院は運営面で苦し い。特例のようなものはないか。
回答 医院側と従業員の過半数代表者が書面で協定を締結した場合、有給休暇を計画的に付与することができます。具体的には、有給休暇のうち5日間については従業員が自由に取得できる分として確保し、5日間を超える部分については計画的に付与します。その際、全従業員を同じ日に取得する一斉付与のほか、個人別に付与する方法などがあります。ご質問のケースでは、先に紹介した有給休暇を計画的に医院で一斉に付与することを検討してはどうでしょうか。具体的には、お盆休みや年末年始の休みのうち例えば5日間について有給休暇を計画的に付与し、残りの日を医院が恩恵的に休暇を与える扱いにするということです。その際、の注意点は、入職して6ヶ月未満で有給休暇が発生していない方や有給休暇の残りが5日以下の方の取り扱いです。この場合、一斉休暇により医院が休診となり、賃金カットを受けることになりますので、休業手当(賃金の6割以上)の支払い等の方策をとる必要があります(昭63.3.14 基発150)。
※なお実際の運用にあたっ ては、協会経営・税務・ス タッフ教育部や社会保険 労務士等に、予め相談を。




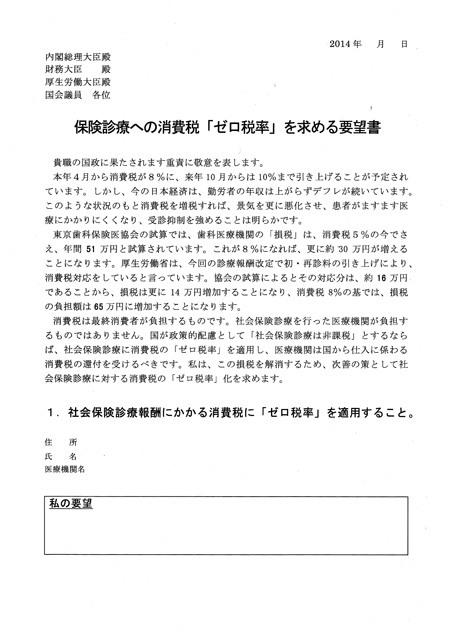
 最後に和田氏は、1人平均う蝕歯数の変遷と歯科医療費・歯科医療費構成割合の年次推移を分析し現状を説明。口腔機能管理による在院日数削減効果や歯科治療需要の将来予測イメージを提示した上で、2014年度歯科診療報酬改定について説明。その中で、昨年秋以降から中医協で協議・検討が加えられている主治医機能について触れ、「歯科ではどのような主治医機能が必要なのか、どのような評価が必要なのか」を議論する必要があり、臨床現場サイドでの検討、提案に期待することを伝えました。さらに、今後の歯科診療報酬を考える上での論点として、①形態回復に加え機能回復の視点、②歯科疾患の重症化予防の視点、③歯科の主治医機能の考え方、④新技術や新医療機器を保険導入するためのツールの活用―という4つの視点を中心に説明。これらのうち④に関しては、新たな技術や医療機器の保険導入などに関する手続きに関し、医療技術評価提案と新規技術届出のほかに、企業による保険適応希望書提出も有効であること等を紹介しました。
最後に和田氏は、1人平均う蝕歯数の変遷と歯科医療費・歯科医療費構成割合の年次推移を分析し現状を説明。口腔機能管理による在院日数削減効果や歯科治療需要の将来予測イメージを提示した上で、2014年度歯科診療報酬改定について説明。その中で、昨年秋以降から中医協で協議・検討が加えられている主治医機能について触れ、「歯科ではどのような主治医機能が必要なのか、どのような評価が必要なのか」を議論する必要があり、臨床現場サイドでの検討、提案に期待することを伝えました。さらに、今後の歯科診療報酬を考える上での論点として、①形態回復に加え機能回復の視点、②歯科疾患の重症化予防の視点、③歯科の主治医機能の考え方、④新技術や新医療機器を保険導入するためのツールの活用―という4つの視点を中心に説明。これらのうち④に関しては、新たな技術や医療機器の保険導入などに関する手続きに関し、医療技術評価提案と新規技術届出のほかに、企業による保険適応希望書提出も有効であること等を紹介しました。